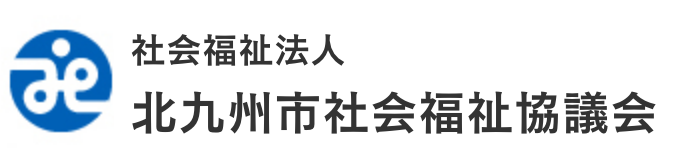コラム21
遺言について考える【第1回】
2014.02.03
長きにわたって働き、間もなく年金を受け取ることができる年齢になると、必ず一度は考えること・・・それは、残りの人生をどう生きるかということと、僅かばかりの蓄えをどのように遺していけばよいかということではないでしょうか。しかし、人の心は移ろいやすいもので、その時々の状況で財産の遺し方についても心変わりするものです。
ところで、遺言は、その人の最終の意思を尊重しようとするものですから、当然に最新のものが有効となりますし、遺言書に日付がなければ、その判断ができないので無効となるのです。極端な話、いくら立派な和紙に毛筆で格調高く作成された遺言書であっても、日付がなければただの紙切れに過ぎませんし、逆に広告の裏面にたどたどしい字で書かれていても、ちゃんと日付の記載があり、その他の要件(自筆であること、対象となる財産が特定されていること、捺印)が揃っていれば、立派な遺言書となるのです。また、最期の時を迎えるまで何通もの遺言書を作成することがあるかもしれませんが、その遺言書の中には、わら半紙に書かれたものから、公証人役場で公正証書として作成したもの等、いろいろな遺言書が混在しているかもしれません。
皆さんの中には、本人がしたためた遺言書より公証人が本人から頼まれて作成した遺言公正証書の方が優先されると思われる方もおられるかもしれませんが、それは誤りです。遺言者の最終意思を尊重しようとするものである以上、同じ遺産を目的としている限り、後の日付で作成されたものが有効となることは当然のことで、それが公正証書であろうが広告の裏面に書かれたものであろうが変わりはないのです。
さて、前置きが長くなってしまいましたが、世の中には、不幸にして配偶者や子ども達から疎まれ、家族との行き来すらなくなっている人や、本来の家族との関係を断ち、現在は別のパートナー(ここからは「愛人」と呼ぶことにします。)と生活を共にしているような人も多いのではないでしょうか。
このような人が、遺産は子ども達ではなく、全て愛人に遺してあげたいと考えても不思議なことではありません。そこまでいかなくても、愛人が生きている間は、何とかして今住んでいるこの自宅から追い出されるようなことがないようにしてあげたいと考えることは、もっともなことかもしれません。果たしてそのようなことができるのでしょうか。
まず、世の中の倫理観に反することではありますが、遺産を全て愛人に遺す方法がないかということから考えてみましょう。「そんなことは簡単なことで、遺言書にそのように書けばいいだけでしょう」と思われるかもしれません。しかし、そんなに簡単にはいかないのです。というのも、配偶者や子ども達には遺留分というものがありますし、遺留分の問題を乗り越えても、遺産の名義を遺言者から愛人に変更する手続きを行わなければ、預金を引き出したり不動産を処分したりすることができないからです。
遺留分とは、相続財産の中で、一定の相続人に遺されるべき財産の割合のことで、相続人が妻や子の場合には相続財産の2分の1、両親の場合には3分の1が対象となり、また、この遺留分は相続分に応じて割り振られることになります。例えば、妻と2人の子どもがいる人が、全財産1000万円を愛人にあげるという遺言書を書いたとしても、2分の1が遺留分となりますので、後に愛人は、最大500万円を妻子から取り戻されてしまう可能性があるということになります。この「可能性がある」という意味ですが、遺留分は、その権利を相続人自らが行使(遺留分減殺請求といいます)しなければ実現できないため、妻子のうちの誰かが遺留分の権利を行使しなければ、行使しない人の相続分に応じた分だけ、愛人の立場で言えば「取り戻される金額が減る」ことになるのです。もし、妻と子ども一人は減殺請求せず、残りの一人だけが遺留分減殺請求をした場合、愛人は125万円(500万円の4分の1)だけをその子どもへ返還すればよいのです。なお、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、相続人が兄弟姉妹だけの場合、遺言者は誰に遠慮することなく愛人に全ての財産を遺すことができるのです。
【3回シリーズ(毎月1日頃掲載)】